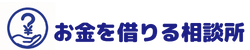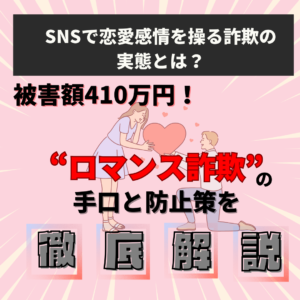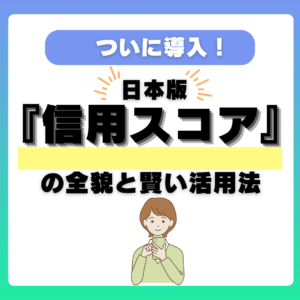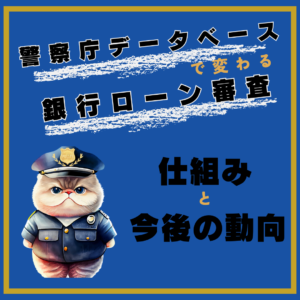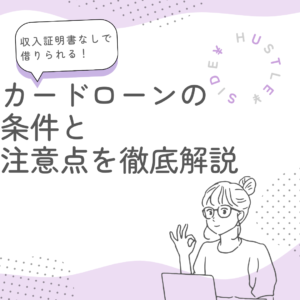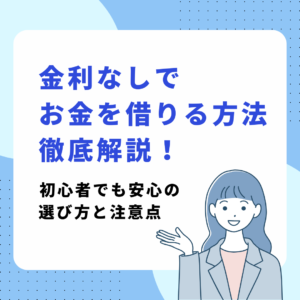高校3年生の子どもを持つ家庭にとって、大学進学は人生の大きな節目です。
しかし、進学には思った以上に費用がかかります。「奨学金を利用すれば何とかなるだろう」と考えていた家庭でも、入学前にかかる費用をどう準備するかを忘れがちです。奨学金は、実際には入学後に支給されるため、受験費用や入学金、最初の授業料は自分たちで準備する必要があります。
この記事では、奨学金制度の注意点や、資金が不足したときの対応策を詳しく紹介します。
また、国の教育ローンや銀行の教育ローンの違いや活用方法も解説します。この記事を読むことで、大学進学に向けた資金計画を立てるための知識が得られます。
この記事でわかること
第1章:奨学金の現実—見落とされがちな問題点
奨学金の仕組みを知ろう
多くの家庭が奨学金を利用していますが、奨学金の仕組みを誤解しているケースも少なくありません。
たとえば、「奨学金があれば、入学前の費用もカバーできる」と思っている人は少なくないでしょう。
しかし、実際には奨学金の振込は大学に入学してから始まります。つまり、受験費用や入学金、初回の授業料は奨学金では支払えないのです。
奨学金がカバーできない費用
以下の費用は、奨学金の振込が開始される前に支払う必要があります。
- 受験費用
・受験料や遠方への受験の交通費
・宿泊費 - 入学金
- 初回の授業料
- 下宿費用(初期費用)
・敷金、礼金、引越し費用など
これらの費用を事前に準備していないと、いざというときに資金が足りなくなり、焦ることになります。
奨学金の説明会で見落としがちな点
奨学金の説明会では、基本的な仕組みについては説明がありますが、細かな注意点までは詳しく話されないことがあります。以下のポイントは特に見落とされがちです。
- 奨学金は入学後に振り込まれる
→ 入学前に必要なお金は別に準備する必要があります。 - 入学後も手続きが必要な場合がある
→ 採用された後でも、必要書類を提出しなければ支給が開始されません。 - 第一種奨学金と第二種奨学金の違い
- 第一種:利子なし(成績や所得制限が厳しい)
- 第二種:利子あり(比較的借りやすい)
奨学金を利用する際は、これらの点を事前に理解し、計画的に準備を進めることが重要です。
第2章:進学費用の内訳と準備すべき金額

大学進学にかかる具体的な費用
大学進学に必要な費用は、学費だけではありません。特に自宅外から通う場合は、下宿費用や生活費が加わり、家計への負担が大きくなります。ここでは、大学進学にかかる主な費用をわかりやすく解説します。
1. 入学前に必要な費用
進学先が決まる前後から、さまざまな費用が発生します。以下はその内訳です。
| 費用項目 | 内容 | 金額の目安(例) |
|---|---|---|
| 受験料 | 大学ごとに支払う受験料 | 3万~5万円/1校 |
| 交通費・宿泊費 | 遠方への受験にかかる費用 | 1万~5万円(距離により異なる) |
| 入学金 | 大学に支払う入学時の一時金 | 20万~30万円 |
| 初回授業料 | 最初の半年分または1年分の授業料 | 40万~80万円 |
| 下宿費用 | 敷金、礼金、引越し費用など | 10万~30万円 |
このように、受験から入学までに必要な費用は合計100万円を超えることも珍しくありません。
2. 入学後に必要な費用
入学後は、授業料のほかにも生活に必要なさまざまな費用が発生します。自宅通学と下宿通学では費用に大きな差があるため、事前に見積もっておくことが重要です。
- 授業料
- 私立大学の場合、年間の授業料は平均して80万~150万円ほどかかります。国公立大学はこの半額程度ですが、それでも年間50万円以上が必要です。
- 教材費・諸経費
- 理系学部や医療系学部は実験道具や専門書などの教材費が高く、年間10万~30万円がかかることもあります。
- 生活費(下宿生の場合)
- 自宅外から通う場合、生活費の負担が大きくなります。
| 項目 | 金額の目安(1か月) | 年間の合計 |
|---|---|---|
| 家賃 | 5万~8万円 | 60万~100万円 |
| 食費 | 3万~5万円 | 36万~60万円 |
| 光熱費 | 1万~2万円 | 12万~24万円 |
| 雑費・交際費 | 1万~2万円 | 12万~24万円 |
下宿生の生活費は、年間150万~200万円ほどになることもあります。
進学費用の準備方法
進学費用をスムーズに準備するためには、いくつかの方法を組み合わせて活用するのがおすすめです。
1. 学資保険
多くの家庭で利用されているのが学資保険です。子どもが小さい頃からコツコツ積み立てておけば、高校卒業時にまとまった金額を受け取ることができます。
メリット
- 計画的に積み立てられる
- 満期時に一括で受け取れるため、入学金や授業料に充てやすい
デメリット
- 途中解約すると元本割れする可能性がある
- インフレによる資金価値の目減りに注意
2. 貯金
進学費用を準備するためには、日頃から計画的に貯金をしておくことが大切です。
- 家計簿をつけて支出を管理する
- 家計簿をつけることで無駄な支出を減らし、効率的に貯金ができます。
- 特別費用口座を作る
- 教育費専用の貯金口座を作り、毎月一定額を積み立てる方法も効果的です。
3. 教育ローン
どうしても費用が足りない場合は、教育ローンを利用するのも一つの手です。次章では、国の教育ローンと銀行ローンについて詳しく解説します。
第3章:国の教育ローンとは?利用のメリットとデメリット
国の教育ローンの概要
「国の教育ローン」とは、日本政策金融公庫が提供する教育一般貸付のことです。このローンは、子どもの教育費を賄うための公的な融資制度で、多くの家庭が利用しています。
利用できる金額と金利
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借入限度額 | 最大350万円(特定条件を満たす場合は450万円まで) |
| 金利(固定) | 年2.35%(2024年11月時点) |
| 返済期間 | 最長18年 |
| 元金据置制度 | 在学期間中は利息のみ支払い、卒業後に元金の返済を開始する仕組み |
このローンは金利が固定されているため、返済額が一定で計画を立てやすいのが特徴です。
また、借入額も高額なため、下宿費用や初年度の授業料をカバーするのに役立ちます。
国の教育ローンを利用するメリット
国の教育ローンにはいくつかのメリットがあります。
- 金利が比較的低い
- 銀行ローンに比べて金利が低いため、返済総額が抑えられます。また、固定金利であるため、返済中に金利が上がる心配がありません。
- 長期返済が可能
- 最長18年まで返済期間を延ばせるため、毎月の返済額を低く抑えることができます。これにより、家計への負担を軽減することが可能です。
- 元金据置制度が使える
- 在学中は利息のみを支払う「元金据置制度」が利用できるため、子どもが在学中は家計に大きな負担をかけずに済みます。
国の教育ローンを利用するデメリット
一方で、注意すべきデメリットもあります。
- 審査に時間がかかる
- 国の教育ローンは申し込んでから審査を経て融資が実行されるまでに時間がかかります。早めに準備を進めないと、必要な時期に間に合わない可能性があります。
- 借入条件に年収制限がある
- 国の教育ローンは、借りる家庭の年収に上限が設定されています。年収が高い家庭は利用できない場合があります。
- 返済期間が長いと利息負担が増える
- 長期間返済することで毎月の負担は減りますが、その分利息の総額が増えるため、総支払額は多くなります。
国の教育ローンの申請手順
国の教育ローンを利用するためには、以下の手順を踏む必要があります。
- 必要書類を用意する
- 借入申込書
- 子どもの在学証明書または合格通知書
- 世帯の収入証明書(源泉徴収票や確定申告書)
- 費用の見積もりがわかる資料(授業料の通知など)
- オンラインまたは窓口で申し込む
- 日本政策金融公庫の公式サイトからオンラインで申し込むことができます。窓口での申請も可能ですが、混雑する時期はオンラインのほうがスムーズです。
- 審査を受ける
- 提出した書類に基づいて審査が行われます。審査期間は通常1~2週間程度です。
- 融資を受け取る
- 審査に通ると、指定した銀行口座に融資額が振り込まれます。
実際の活用事例
事例1:地方在住の家庭が利用したケース
地方に住むAさんの家庭は、長男の進学で東京の私立大学を受験しました。受験費用や入学費用、引越し費用が一時的に必要になり、国の教育ローンを350万円借りました。在学中は元金据置制度を利用し、卒業後に子どもが就職した際に返済を手伝ってもらう形を取りました。
事例2:複数の子どもを抱える家庭の場合
Bさんの家庭には3人の子どもがいて、長男に続き次男も大学進学を控えていました。家計の負担が大きくなることを見越して、長男の進学時に国の教育ローンを利用し、次男の進学時にも再度申し込むことで資金を確保しました。
第4章:銀行の教育ローンを利用する際のポイント
銀行の教育ローンの概要
銀行でも、大学進学に伴う教育費用を補うための「教育ローン」が提供されています。国の教育ローンと異なり、銀行ごとに条件やサービス内容が異なるため、利用する際にはそれぞれの特徴をよく比較することが重要です。
銀行の教育ローンの特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借入限度額 | 500万円~1,000万円程度 |
| 金利(変動または固定) | 1.5%~3.5%(銀行やプランによって異なる) |
| 返済期間 | 最長10年~15年 |
| 担保や保証人 | 保証人が必要な場合あり(保証会社を利用するケースも多い) |
銀行ローンの最大の魅力は、借入限度額が高いことです。特に医学部や私立大学の学費が高いケースでは、国の教育ローンでは賄いきれない分を補うために銀行ローンを利用することが有効です。
銀行の教育ローンのメリット
- 高額な借入が可能
- 銀行ローンは国の教育ローンに比べて借入限度額が高く、最大1,000万円まで借りられるプランもあります。医療系や理系の学部など、学費が高額になりやすい場合に役立ちます。
- 金利が低いプランもある
- 銀行ローンには、国の教育ローンよりも低金利で提供されているプランもあります。特に、信用度の高い顧客には優遇金利が適用されることが多く、返済総額を抑えることができます。
- 多様な返済方法が選べる
- 銀行ローンでは、一括借入型や限度額内で繰り返し借り入れができる「カードローン型」など、さまざまな返済方法を選択できます。これにより、必要なタイミングで柔軟に資金を確保できるのが利点です。
銀行の教育ローンのデメリット
- 審査が厳しい
- 銀行の教育ローンは、国の教育ローンに比べて審査基準が厳しい傾向にあります。特に、安定した収入が求められ、年収200万円以上が条件となることが多いです。
- 変動金利のリスク
- 銀行ローンの多くは変動金利を採用しています。そのため、将来的に金利が上昇すると、返済額が増えるリスクがあります。固定金利型を選べばこのリスクを抑えられますが、その分初期金利はやや高めに設定されています。
- 手続きが複雑
- 銀行によって必要な書類や申請手続きが異なり、準備に手間がかかることがあります。また、担保や保証人が必要な場合もあり、スムーズに借りられない場合があります。
銀行の教育ローンを選ぶ際のポイント
銀行の教育ローンを選ぶときには、以下の点を比較して検討しましょう。
- 金利の種類と水準
- 変動金利型と固定金利型を比較し、総返済額が少なくなるものを選びましょう。
- 返済期間
- 返済期間が長いほど月々の負担は軽くなりますが、その分利息が増えるので注意が必要です。
- 手数料や諸費用
- 銀行によっては、借入時に手数料や保証料が発生することがあります。これも総費用に影響するため、事前に確認しましょう。
実際の活用事例
事例1:変動金利型ローンを利用した家庭の例
Cさんの家庭では、長女が私立の理系大学に進学する際、年間150万円以上の学費が必要となりました。国の教育ローンでは不足分を補えないため、銀行の教育ローンを利用しました。金利が低い変動金利型を選び、毎月の返済額を抑えつつ、金利上昇リスクを見極めながら返済を進めています。
事例2:固定金利型ローンを選んだ家庭の例
Dさんの家庭は、長男の進学で一時的に500万円の資金が必要となりました。変動金利型よりもやや金利が高いものの、将来の金利上昇を避けるために固定金利型を選択。毎月一定額の返済を続け、計画的に家計管理をしています。
第5章:教育資金不足に備えるための家計管理術

進学費用に備えた家計管理の重要性
大学進学は、家庭の財政に大きな負担をかけるイベントです。
そのため、奨学金や教育ローンを利用するだけでなく、日頃から計画的に家計管理を行い、資金を準備することが重要です。この章では、教育資金不足を防ぐための効果的な家計管理術を紹介します。
教育資金専用の貯金口座を作る
進学費用の準備を始める際は、教育資金専用の貯金口座を作成するのが効果的です。この口座を作ることで、普段の家計費と混ざらず、明確な目標金額を設定しやすくなります。
具体的な方法
- 毎月の収入から無理のない範囲で一定額を積み立てる
- ボーナスなどの臨時収入があった際には、一部をこの口座に入金する
- 貯金目標額を設定し、進捗を定期的に確認する
家計簿をつけて支出を見直す
家計管理の基本は、支出を把握することです。家計簿をつけることで、無駄な支出を見直し、効率よく貯金を増やすことができます。
学資保険を活用する
学資保険は、教育資金を計画的に準備するための一般的な方法です。特に、小さい頃から積み立てを始めると、進学時にまとまった資金を受け取ることができるため、多くの家庭で利用されています。
注意点
- 途中解約すると元本割れするリスクがある
- 保険料の支払いが家計に負担をかけすぎないよう、無理のない範囲で契約することが大切
4. 節約だけでなく副収入を考える
節約だけでなく、収入を増やす方法を考えることも資金不足を防ぐ効果的な手段です。
子どもにも協力してもらう
教育資金は親だけが準備するものと思われがちですが、子ども自身にも協力をお願いすることで、資金計画がより現実的になります。
子どもができること
- バイトをして貯金する
- 高校生や大学生になれば、アルバイトをすることで進学費用の一部を自分で準備できます。これにより、親の負担を減らすことができます。
- 奨学金を自分で管理する
- 受け取った奨学金を計画的に使うよう、子ども自身に資金管理を任せることで、金銭感覚を養うことができます。
進学費用の準備を成功させるためのポイントまとめ
- 長期的な視点で計画を立てる
- 短期間で大きな額を準備するのは難しいため、早めに計画を始め、少しずつ積み立てることが大切です。
- 家族全員で進学費用について話し合う
- 親だけでなく、子どもも含めた家族全員で教育費について話し合い、目標を共有することで、協力しながら計画を進めることができます。
- 無理のない貯金ペースを維持する
- 無理な節約は家族の生活にストレスを与えます。無理のないペースで続けられることを重視しましょう。
第6章:まとめと次のステップ
まとめ:奨学金や教育ローンだけに頼らない資金計画の重要性
今回の記事では、奨学金制度の注意点や教育費用の準備方法、国の教育ローンと銀行の教育ローンの活用法、そして家計管理術について詳しく解説しました。大学進学は、家族にとって大きなライフイベントです。そのため、「奨学金さえあれば大丈夫」という楽観的な考えではなく、入学前から具体的な資金計画を立てることが非常に重要です。
特に、奨学金は入学後に支給されるため、入学前に必要な費用(受験料・入学金・授業料など)は別途準備する必要がある点を忘れないようにしましょう。
また、資金不足を補うために教育ローンを利用する場合も、それぞれのローンの特徴をしっかり理解しておくことが大切です。家計を圧迫しないためには、無理のない節約や収入増加の方法を取り入れ、長期的に安定した資金準備を進めることが成功のカギになります。
次のステップ:具体的な行動を始めよう
- 奨学金と教育ローンについて詳しく調べる
- 日本学生支援機構(JASSO)の公式サイトや日本政策金融公庫の教育ローン情報を確認し、条件や手続きの詳細を理解しましょう。
- 家計の現状を把握する
- 家計簿をつけて収入と支出のバランスを見直し、どのくらい貯金に回せるかを確認します。特に固定費を見直すことが効果的です。
- 教育資金専用口座を作る
- 目標額を設定し、毎月一定額を積み立てる計画を立てましょう。ボーナスや臨時収入があった際には、積極的に追加貯金を行います。
- 家族で話し合いをする
- 家族全員で進学費用の計画を共有し、協力し合うことが大切です。子どもにも進学費用に関する現状を理解してもらい、自分でできることを考えてもらいましょう。
この記事の活用法
- 教育費用を考える際の参考資料として
- この記事をもとに、奨学金や教育ローンの活用法を検討し、家計管理術を取り入れてください。
- 進学を控えた家庭での話し合いの材料として
- 家族で教育費用について話し合う際に、この記事を読んで現状を把握し、計画を立てるための土台にしてください。
- 知人や友人への情報提供として
- 同じように進学費用に悩んでいる知人や友人にこの記事を共有し、役立つ情報を提供しましょう。