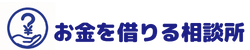お金の貸し借りは、親しい友人や家族との間でもトラブルの原因になりやすいものです。実際、裁判所に持ち込まれる民事紛争の多くは「金銭トラブル」であり、口約束だけで貸した結果、返済日や利息をめぐって「言った・言わない」の水掛け論になるケースが少なくありません。
このようなトラブルを防ぐために有効なのが、借用書や金銭消費貸借契約書といった契約書の作成です。これらの書類には、返済期日・返済方法・利息・遅延損害金・期限の利益の喪失条件などを明記でき、将来的に返済が滞った場合でも強力な証拠となります。特に、印紙税法に基づく収入印紙の貼付や、利息制限法に定められた上限金利を遵守しておくことで、契約の効力がより確実なものになります。
とはいえ、借用書や金銭消費貸借契約書を作ろうとすると「親しいのに契約書なんて必要なの?」「信用していないのか?」と感情的に反発されることもあります。しかし、経験上そのように契約を嫌がる相手ほど返済トラブルを起こしやすく、最悪の場合には裁判や強制執行といった法的手続きに発展する可能性すらあります。
この記事では、行政書士監修のもとで、借用書・金銭消費貸借契約書の違い、正しい書き方、作成時の注意点、法的効力について詳しく解説します。これから個人間でお金を貸す予定がある方、あるいは「もし返してもらえなかったらどうしよう」と不安を抱えている方は、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
親しき仲にも礼儀あり。借用書作成のススメ
人間関係が壊れる原因の第一位は「お金のトラブル」といわれています。親子・夫婦・友人といった親しい関係であっても、金銭の貸し借りがきっかけで長年の信頼関係が崩れてしまうケースは珍しくありません。だからこそ、個人間融資では必ず 借用書 を作成することが大切です。
民法の条文上、口約束だけでも金銭消費貸借契約は成立します。しかし、返済期日や利息の有無をめぐって「言った・言わない」の争いになれば、水掛け論となり解決が難しくなります。実際、裁判所に持ち込まれる金銭トラブルの多くは「契約書を作らなかった」ことが原因です。
その点、借用書や金銭消費貸借契約書を作成しておけば、返済日・利息・遅延損害金などの条件が明確になり、トラブルを未然に防ぐことができます。書面は裁判でも有効な証拠となり、貸主・借主双方を守る重要な役割を果たします。
もっとも、借用書の作成を持ち出すと「親友なのに借用書を書くのか?」「信用していないのか?」と感情的に反発されることもあります。しかし、経験上そうした態度を示す人ほど、返済が遅れたり約束を破ったりしやすく、最悪の場合は口論や暴力沙汰に発展する危険すらあります。
「貧すれば鈍する」という言葉の通り、お金に困ったときには冷静な判断ができなくなるものです。だからこそ、お金を貸す側は自分の身を守るために毅然とした態度で臨みましょう。借用書を書きたがらない相手には、きっぱりと貸さないと決めることも大切です。精神的な負担や後悔を避けるためにも、「書面化してくれる人にだけ貸す」と割り切るのが賢明です。
もし相手が借用書の作成に応じるのであれば、利息・返済期日・期限の利益の条件を盛り込んだ正式な文書を準備しましょう。次の章では、実際の借用書や金銭消費貸借契約書の書式例を紹介します。
「借用書」と「金銭消費貸借契約書」とは
「借用書」と「金銭消費貸借契約書」は、いずれも 金銭の貸し借りを証明するための契約書類 です。どちらの文書も「お金を貸した・借りた」という事実を明確に残し、将来的なトラブルを防ぐための役割を果たします。
共通して盛り込むべき内容は次のとおりです。
- 貸し借りの事実を証明する条項(いつ・誰が・いくら貸したのか)
- 返済期日や返済方法(一括返済か分割返済か、振込先口座の指定など)
- 利息の取り決め(利息制限法の範囲内で設定)
- 返済が滞った場合の措置(遅延損害金や期限の利益の喪失条件など)
このように、借用書と金銭消費貸借契約書はどちらも「契約内容を文字で残す」という点では共通しています。しかし、保管方法や署名のルールに違いがあるのです。
- 借用書:借主(お金を借りる人)が署名・押印し、貸主が保管する文書。簡易に作成できるが、貸主側に有利な形式。
- 金銭消費貸借契約書:貸主と借主の双方が署名・押印し、各自が1通ずつ保管する。高額の融資や分割返済の場合に適しており、より正式な契約書としての効力が期待できる。
つまり、借用書は「シンプルで手軽」、金銭消費貸借契約書は「より厳格で対等性がある契約書」といえます。
どちらを選ぶべきかは、貸し借りの金額や返済方法、そして将来的なトラブル回避をどの程度重視するかによって決まります。金額が大きい、返済が長期にわたる場合は、できるだけ金銭消費貸借契約書を作成するのがおすすめです。
借用書とは
借用書とは、借主(お金を借りる側)が自ら署名・押印し、貸主(お金を貸す側)が保管する契約書類 のことです。連帯保証人を付ける場合には、保証人の署名・押印も必要になりますが、貸主自身の署名は必須ではありません。そのため、形式としては 金銭消費貸借契約書よりも簡単に作成できる のが大きな特徴です。
借用書を作成する最大のメリットは、「お金を確かに借りた」という証拠が残ること です。口約束だけでは後々「借りていない」「そんな条件は聞いていない」といった水掛け論に発展する恐れがありますが、借用書に署名・押印しておけば、契約内容が明確になり、裁判になった際にも有力な証拠として活用できます。
さらに、借用書は比較的シンプルな書式で済むため、少額の貸し借りや親しい間柄での融資でも取り入れやすいという利点があります。とはいえ、金額が高額になったり、分割返済や利息を伴う場合には、より厳密で対等性のある 金銭消費貸借契約書 を作成した方が安心です。
借用書は「簡単に作成できるけれど、効力はしっかり残る」便利な契約書。個人間融資でトラブルを避けるための第一歩として、必ず用意しておくことをおすすめします。
借用書の例
実際に借用書を作成する際は、必要な項目を漏れなく記載することが大切です。以下に、基本的な借用書のサンプル例をご紹介します。
借用書
お金 貸す蔵 殿
私は貴殿より令和5年1月1日、金壱百弐拾萬円を借り受けました。
上記、借り入れにつき、令和6年1月1日限り、一括にて返済します。
利息は年5%とし、毎月15日に限り、その月分を支払います。
遅延損害金は年10%とします。
借主について、次の事由が一つでも生じた場合には、借主は期限の利益を失い、直ちに残金を一括で支払うものとします。
- 利息の支払いを一度でも怠ったとき。
- 民事再生の手続きもしくは破産の申し立てがあったとき。
令和5年1月1日
住所 東京都△△区□□-1-2-3
氏名 お金 借り太郎 印
このように、借用書には「借入日」「金額」「返済期日」「利息」「遅延損害金」「期限の利益の喪失条件」といった重要な要素を必ず明記する必要があります。特に 金額は漢数字で記載すること によって、改ざんを防止できます。
また、連帯保証人を立てる場合は、保証人の署名・住所・押印を追記しておくと、返済が滞ったときに貸主が保証人に対しても請求できるため、より法的効力が高まります。
この借用書の例では、令和5年1月1日に「お金借り太郎」さんが「お金貸す蔵」さんから120万円を借りたことが明記されています。返済期日は令和6年1月1日で、利息は年率5%。つまり 120万円 × 5% ÷ 12ヶ月 = 月額5,000円 を毎月15日に支払う取り決めです。
返済方法を銀行振込や現金手渡しにするかは、当事者間で自由に取り決められます。その場合も必ず借用書に具体的に記載しておきましょう。
期限の利益について
借用書の例文にも登場した「期限の利益」という言葉は、契約を結ぶ上で非常に重要な法律用語です。
期限の利益とは、契約で定められた返済期日までは借主(債務者)が返済しなくても良いという権利 を意味します(民法136条)。つまり、貸主(債権者)が「事情が変わったから、今すぐ残りの100万円を返してくれ」と急に要求してきたとしても、返済期日が到来するまでは借主は応じなくても良い、というのが「期限の利益」です。
ただし、この権利は絶対的なものではありません。契約書にあらかじめ 期限の利益を喪失する条件 を定めておくことで、借主が返済期日前であっても一括返済を請求される可能性が出てきます。これを「期限の利益の喪失」と呼びます。
期限の利益を喪失する条件の例
- 利息の支払いを一度でも怠った場合
- 返済日を繰り返し遅延した場合
- 自己破産や民事再生などの手続きを申し立てた場合
- 差押えや仮差押えを受けた場合
上記のような状況に陥ると、貸主は「期限を待つ必要はない」として、借主に対して即時の一括返済を求めることが可能になります。
たとえば、先ほどの借用書例では「利息の支払いを一度でも怠ったとき」「自己破産を申し立てたとき」などが条件として記載されています。このように契約時に明記しておけば、貸主は不測の事態に備えることができ、借主も「返済遅延=期限の利益喪失」になると理解できるため、トラブル防止に役立ちます。
- 期限の利益は借主を守る大切な権利だが、条件付きで喪失する可能性がある
- 契約書に条件をきちんと記載しておくことで、双方にとって安心できる契約になる
- 借主は「条件を満たせば期限前でも一括請求される」ことを理解して契約に臨む必要がある
借用書や金銭消費貸借契約書を作成する際は、必ず 期限の利益の有無と喪失条件を明記すること がトラブル回避の鍵となります。
金銭消費貸借契約書とは
金銭消費貸借契約書(きんせんしょうひたいしゃくけいやくしょ) とは、貸主(お金を貸す側)と借主(お金を借りる側)の双方が署名・押印し、それぞれが1通ずつ保管する正式な契約書のことです。連帯保証人を立てる場合には、貸主・借主・保証人の三者が署名・押印を行い、契約書を3通作成して各自が保管するのが原則です。
このように関係者全員が同じ契約書を持つことで、後々「言った・言わない」「契約内容を知らなかった」という食い違いを防ぐことができます。借用書が「借主だけが署名して貸主が保管するシンプルな書類」であるのに対して、金銭消費貸借契約書は 当事者全員の合意を記録する、より厳密で信頼性の高い契約文書 といえます。
特に以下のようなケースでは、借用書よりも金銭消費貸借契約書を選んだほうが安心です。
- 高額な金銭の貸し借りを行う場合
- 返済方法が分割払いになる場合
- 利息や遅延損害金の取り決めをする場合
- 連帯保証人を付ける必要がある場合
また、契約書に署名・押印するだけでなく、返済期日・返済方法・利率・遅延損害金・期限の利益喪失条件 などを明確に記載しておくことで、将来的に裁判などの法的トラブルになった際にも有力な証拠として効力を発揮します。
つまり、金銭消費貸借契約書は「しっかり返済条件を取り決めたい場合」や「お金の貸し借りにリスクが伴う場合」に不可欠な契約文書です。個人間融資だけでなく、事業資金の貸し借りなどでも幅広く活用されています。
金銭消費貸借契約書の例
実際にどのような形で金銭消費貸借契約書を作成するのか、雛形を示します。以下は典型的な契約書の例文です。
金銭消費貸借契約書
貸主(甲) お金 貸す蔵
借主(乙) お金 借り太郎
甲と乙は、次のとおり金銭消費貸借契約を締結する。
第1条(貸借)
甲は乙に対し、本日、金壱百弐拾萬円を貸し渡し、乙はこれを借り受け受領した。
第2条(弁済期)
乙は甲に対し、令和5年1月1日に限り、甲の住所に持参もしくは送金して返済する。なお、送金先銀行口座は甲が別途指定する。
第3条(利息)
乙は甲に対し、元金に対し年5%の利息を毎月15日に限り、その月分を支払うこととする。なお支払いの方法は第2条と同じとする。
第4条(遅延損害金)
乙が支払いを遅滞したときは、遅滞した日の翌日から完済まで、年10%の遅延損害金を支払うものとする。なお支払い方法は第2条と同じとする。
第5条(期限の利益の喪失)
乙は、次のいずれかに該当する場合、甲からの通知、催告を要せず当然に期限の利益を失い、直ちに、残金を一括で返済しなければならないものとする。
- 利息の支払いを一度でも怠ったとき。
- 民事再生手続きもしくは破産の申し立てがあったとき。
上記の金銭消費貸借を証するため、本書2通を作成し、各当事者署名捺印の上、各1通を保管するものとする。
令和5年1月1日
貸主(甲)住所 東京都△△区□□-1-2-3
氏名 お金 貸す蔵 印
借主(乙)住所 東京都△△区□□-1-2-3
氏名 お金 借り太郎 印
このように、借主と貸主が署名・押印を行い、それぞれが1通ずつ保管する のが金銭消費貸借契約書の基本です。連帯保証人を立てる場合は、保証人も署名・押印を行い、契約書を3通作成して三者で保管します。
上記の例では、令和5年1月1日に「お金借り太郎」さんが「お金貸す蔵」さんから120万円を借りる契約を締結しています。返済日は翌年の令和6年1月1日、利息は年率5%で毎月15日に支払い、延滞時には年10%の遅延損害金を支払うことが明記されています。
さらに、この契約書では返済方法(持参または送金)、利息の支払日、遅延損害金の計算方法、そして「期限の利益の喪失」条件が細かく定められている点も重要です。これらを明文化することで、後にトラブルが発生しても裁判の証拠として強い効力を発揮します。
金銭消費貸借契約書は借用書よりも形式的には複雑ですが、高額な融資・分割返済・利息の取り決めがある場合には必須 の契約書といえるでしょう。
借用書・金銭消費貸借契約書を作成するときの注意点
個人間でお金を貸し借りする際に作成する 借用書 や 金銭消費貸借契約書 は、法律的に効力を持つ重要な契約文書です。しかし、作り方を誤ると「無効扱い」や「トラブルの原因」になりかねません。ここでは、実務で必ず押さえておくべき作成時の注意点を整理します。
基本的な注意点
- 筆記具は消せないものを使用:鉛筆や消えるボールペンは厳禁。必ず消せないボールペンや万年筆を使用します。
- 署名は直筆:パソコンで作成しても問題ありませんが、最終的に署名は必ず自筆で行いましょう。代筆は無効になります。
- 押印は実印推奨:拇印(親指または人差し指)でも構いませんが、印鑑証明書を添付した実印の方が法的効力が強くなります。
- 契約日を正しく記載:契約日=お金を貸し渡した日です。利息計算や時効の起算日になるため、必ず明記しましょう。
- 連帯保証人がいる場合:保証人の署名・押印を忘れずに。保証人欄が不備だと効力が限定されます。
- 金額は漢数字で記載:「壱・弐・参」などの漢数字を使うことで改ざん防止になります。
返済期日と返済方法を明確にする
返済条件は契約書の中でも最重要ポイントです。あいまいにしておくと後にトラブルの元になります。
- 一括返済の記載例
「令和5年12月末日限り、指定の銀行口座に送金して返済する。振込手数料は借主負担とする。」 - 分割返済の記載例
「元金を12回に分割し、毎月末日限り金20万円を送金。振込手数料は借主負担とする。」
「最終回は令和6年12月末日に残額10万円を返済する。」
こうした具体的な記載がなければ、民法の原則に従うことになりますが、一般人にとっては理解しにくく不要な争いの火種になります。
金利と遅延損害金の取り決め
借用書・契約書に金利を記載する場合は、利息制限法 の上限を超えないように注意が必要です。
- 元本10万円未満:年20%(遅延損害金は29.2%まで)
- 元本10~100万円未満:年18%(遅延損害金は26.28%まで)
- 元本100万円以上:年15%(遅延損害金は20.19%まで)
遅延損害金の計算式は以下のとおりです。
元金 × 遅延損害利率 × 経過日数 ÷ 365日
違法な高金利を記載すると契約が無効となる可能性があるため、必ず法定上限内で設定しましょう。
「期限の利益」の喪失条件を定める
「期限の利益」とは、契約で定めた返済期日まで借主が返済を猶予される権利のことです。通常は貸主が途中で返済を迫ることはできません。
ただし、以下のようなケースでは「期限の利益を失う」旨を契約に明記しておきましょう。
- 支払いを2回以上遅れた場合
- 仮差押や差押を受けた場合
- 破産・民事再生などの法的手続きを申し立てた場合
これにより、貸主は返済期日前でも残額の一括請求が可能になり、債権保全のリスクを大幅に下げられます。

借用書や金銭消費貸借契約書を作成するときは、署名・押印・契約日・返済条件・金利・遅延損害金・期限の利益といった要素をもれなく記載し、法的効力を確実なものにすることが重要です。特に、金利の上限や連帯保証人の署名漏れは契約無効に直結するため細心の注意を払いましょう。
借用書・金銭消費貸借契約書の効力
「借用書」や「金銭消費貸借契約書」は、単なる紙切れではなく、法律的にも効力を持つ正式な契約書です。正しく作成・保管しておくことで、個人間のお金の貸し借りにおけるリスクを大幅に減らすことができます。ここでは、それらの書類が持つ主な効力を整理して解説します。
トラブルの防止
借用書や契約書を作成すると、金銭貸借の事実・返済条件・金利・返済期日 が明確になります。その結果、よくある「言った・言わない」の水掛け論や、「そんな約束はしていない」という不毛な争いを防止できます。特に親族や友人間の貸し借りでは、感情的なトラブルを避けるためにも文書化が必須です。
返済をスムーズにする
返済スケジュールや返済方法(銀行振込・現金手渡しなど)をあらかじめ契約書に記載しておけば、借主も貸主も安心してやり取りできます。
- 返済日を明記 → 毎月の返済が習慣化しやすい
- 利息や遅延損害金を明記 → 不払いが発生した場合の対応が明確になる
こうした取り決めがあることで、後々の返済トラブルを最小限に抑えられます。
裁判の証拠になる
最も重要なのが、借用書・契約書は 裁判の証拠として利用できる という点です。
もし借主が返済を怠った場合でも、契約書があれば貸主は裁判で有利に立証できます。裁判所は、口約束ではなく「署名・押印のある書面」を重視します。
特に、借用書よりも厳格な形式をとる金銭消費貸借契約書は、証拠能力が高く、強制執行の根拠としても活用しやすい ため、大きな金額を貸す場合には必ず用意しておきたい契約文書です。



借用書・金銭消費貸借契約書は、トラブル防止・返済の円滑化・裁判での証拠能力確保という3つの大きな効力を持ちます。
個人間融資における安心と安全を守るためには、必ず契約書を作成しておくことが不可欠です。
公正証書にすれば“回収力”が段違い|強制執行認諾・債務名義・作成手順【行政書士監修】
「借用書」や「金銭消費貸借契約書」の証拠力をさらに一段引き上げたいなら、公正証書(強制執行認諾文言付き)を検討しましょう。公証役場で公証人が作成するため真正性・証拠力が高く、返済滞納時には裁判を経ずに差押え等の強制執行へ直行できる=債務名義化できる点が最大のメリット。個人間融資のトラブル防止と債権回収の実効性を同時に担保します。
公正証書とは?|強制執行認諾文言があると債務名義として機能する
公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書のことを指します。個人間融資や金銭消費貸借契約の場面でこの公正証書を作成しておけば、契約内容が法的に強力な裏付けを持つため、単なる借用書や契約書とは比較にならないほどの証拠力と回収力を発揮します。
特に重要なのが、強制執行認諾文言を盛り込める点です。これは「本証書に基づく金銭債務について、直ちに強制執行に服する」という趣旨の条項であり、これを契約書に付けて公正証書化しておくと、借主が返済を滞納した瞬間に裁判を経ずに強制執行へ進めることが可能になります。具体的には、公正証書をもとに執行文の付与を受け、そのまま裁判所に強制執行申立てを行い、給与や預貯金、不動産などを差し押さえることができるのです。
このように強制執行認諾文言付きの公正証書は、いわゆる「債務名義」としての効力を持ちます。通常、借用書や金銭消費貸借契約書だけでは、返済が滞った際にまず訴訟を起こし、判決を得てからでなければ差押えなどの手続きを進められません。しかし、公正証書であれば裁判を省略でき、時間とコストを大幅に削減しながら債権回収を進められる点が最大の魅力です。
つまり、公正証書とは「契約の存在を明確にする」だけでなく、「返済が滞ったときに即座に行動できる強力な回収手段」として機能する法的文書です。借用書や金銭消費貸借契約書よりも格段に実効性が高いため、高額の貸し借りや分割返済、親族間以外の融資などでは、公正証書を利用するのが極めて有効だといえるでしょう。
どんなケースに向いている?|高額貸付・分割返済・保証・担保付き契約に最適
公正証書は、単純に数万円の貸し借りを記録するだけではなく、高額な貸付や複雑な返済条件を伴う契約にこそ威力を発揮します。特に以下のようなケースでは、借用書や金銭消費貸借契約書では不十分で、公正証書を作成しておくことがリスク回避につながります。
まず、高額の貸付を行う場合です。数十万円から数百万円単位の貸し借りでは、返済トラブルが発生した際の損失も大きくなります。そのため、裁判を経ずに強制執行できる公正証書を作成しておくことが、貸主にとって強力な安心材料となります。
次に、分割返済や利息・遅延損害金の取り決めがある場合です。毎月の返済スケジュールや利息の支払いが伴う契約では、返済遅延や未払いのリスクが高まります。こうした条件を明文化した公正証書を用意しておけば、返済トラブル時に「期限の利益喪失」を根拠に一括弁済を請求することが可能になります。
さらに、連帯保証人を付ける場合や担保を設定する場合にも公正証書は有効です。不動産・動産・売掛金などの担保権を設定しておくことで、返済不能となった際に担保からの回収を図ることができます。保証人についても、公正証書に署名・押印しておけば、主債務者だけでなく連帯保証人に対しても法的効力を及ぼせる点が大きなメリットです。
最後に、将来的なリスクを見据えて「強制執行までを視野に入れたい場合」です。公正証書は、債務名義としての効力を持つため、借主が返済を怠った瞬間に差押えなどの法的手続きに移行できます。これは通常の借用書や契約書では不可能な強みであり、確実に回収したい貸主にとっては必須の手段といえるでしょう。
つまり、公正証書は「高額・分割・保証・担保」という複雑な条件が絡む契約に最適であり、債権回収の実効性を最大化する唯一の契約書といっても過言ではありません。
公正証書を作成するときの準備書類|当日迷わないためのチェックリスト
公正証書を作成する際には、公証役場で必要な書類がそろっていないと手続きが進まず、再訪が必要になるケースもあります。事前に準備を整えておくことで、スムーズに契約を成立させられます。ここでは、公正証書作成に必須となる代表的な書類を整理してご紹介します。
まず、貸主・借主・連帯保証人(必要な場合)それぞれの本人確認書類が必要です。運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きの公的証明書を用意しておきましょう。本人確認は公証人が最も重視する部分であり、不備があると即座に手続きが止まってしまいます。
次に、実印と印鑑証明書です。公正証書は裁判での証拠能力を持ち、場合によっては強制執行に直結する「債務名義」となるため、認印や拇印よりも法的効力が確実な実印を使用するのが実務上の鉄則です。印鑑証明書は発行から3か月以内のものを用意してください。
さらに、契約条件を整理した契約条件メモも必須です。たとえば、元本の金額、返済期日や返済スケジュール、返済方法(銀行振込・口座指定)、利率(利息制限法の範囲内)、遅延損害金の利率、期限の利益の喪失条件、違約金や担保の有無などを詳細にまとめておきましょう。こうした条件を事前に明文化しておくことで、公証役場での打ち合わせもスムーズになります。
なお、代理人が公証役場に出向く場合には委任状が必要です。委任状の書式は公証役場ごとに異なるため、事前に確認し、指定の様式に合わせて準備しましょう。
このように、公正証書の作成には 本人確認書類・実印・印鑑証明書・契約条件メモ・委任状といった重要書類が不可欠です。準備不足は手続きの遅延や無駄な再訪につながるため、前もってしっかりとチェックリスト化しておくことをおすすめします。
公正証書に盛り込むべき典型条項
公正証書を作成する際には、記載内容が曖昧だと将来の紛争防止や強制執行の実効性が損なわれる恐れがあります。そのため、実務では定型的に盛り込まれる「典型条項」を漏れなく記載することが重要です。以下では、公正証書のドラフトを作成するうえで必須となる主要条項を整理します。
まず第1条(元本・貸付)では、貸し付ける金額と受領日を明確に特定します。金額は必ず算用数字と漢数字を併記し、改ざん防止を徹底するのが基本です。
次に第2条(返済方法)です。一括返済か分割返済かを明示し、振込期日・振込先口座・振込手数料の負担者まで詳細に記載します。特に分割払いの場合は、返済スケジュールを具体的に示すことで、返済遅延をめぐるトラブルを防げます。
第3条(利息)では、利息制限法の上限を超えない範囲で利率を設定し、年利・月利をどのように計算するかを明記します。あわせて、第4条(遅延損害金)を定めておくことで、返済が遅れた場合の追加負担を明確化できます。計算式として「元金 × 遅延損害利率 × 経過日数 ÷ 365日」を契約書に記載しておくと、後々の解釈違いを防げます。
また、第5条(期限の利益喪失条項)も欠かせません。支払遅延が一定回数発生した場合、自己破産や民事再生を申し立てた場合、差押えを受けた場合などを条件として、期限の利益を喪失する旨を規定しておくことで、貸主は直ちに残額の一括返済を請求できるようになります。
さらに第6条(連帯保証)を設け、保証人が負う範囲を「元金・利息・遅延損害金・訴訟費用等」にまで及ぼすことを明確にしておくと、債権回収の実効性が高まります。
最も重要なのが第7条(強制執行認諾文言)です。ここで「本契約に基づく金銭債務について、直ちに強制執行に服する」旨を明記しておけば、裁判を経ることなく債務名義として強制執行に移行できます。
必要に応じて、担保条項(不動産や動産に対する担保設定)、専属的合意管轄条項(訴訟を提起する裁判所の指定)、振込不能時の通知義務なども追加されます。こうした条項をバランスよく盛り込むことで、公正証書の実効性は飛躍的に高まり、将来の回収リスクを大幅に低減できます。
公正証書作成にかかる費用相場とスケジュールの目安
公正証書を作成する際に気になるのが「どれくらい費用がかかるのか」「どの程度の日数で完成するのか」という点です。実際の手続きでは、公証人の手数料・書類準備の時間・予約の混雑状況などによって変動しますが、一般的な目安を把握しておけば安心です。
まず、公証人手数料は元本額(貸付金額)によって段階的に決まります。数万円程度の少額貸付なら数千円で済みますが、数百万円~数千万円規模の高額貸付になると数万円~十数万円程度になるケースもあります。金額が大きいほど逓増する仕組みになっているため、高額融資ではあらかじめ公証役場に見積もりを取っておくのが賢明です。
次に、作成スケジュールについて。契約条件がすでに固まっていれば、公証役場への予約→草案の確認→面前での署名・押印といった流れで、通常は数日から1週間程度で公正証書が完成します。事前に契約内容を整理したメモや下書きを用意しておけば、スムーズに進み、最短で数日で受け取れるケースもあります。ただし、繁忙期や支店の混雑状況によっては日程が延びる場合もあるため、余裕をもった計画が必要です。
また、注意したいのが印紙税です。公正証書は「公文書」にあたるため、印紙税は非課税となります。そのため、私文書として作成する借用書や覚書とは異なり、収入印紙を貼る必要はありません。ただし、公正証書と併せて私文書の覚書を別途作成した場合は印紙税の対象となることがあるため、その点は誤解しないようにしましょう。
このように、公正証書の作成には数千円~数万円の費用と、数日から1週間程度の期間が必要となります。事前に費用相場と手続きスケジュールを把握しておくことで、余計なトラブルや時間ロスを防ぎ、安心して契約を進めることができます。
公正証書の作成手順
公正証書は、作成の手順をきちんと理解しておくことでスムーズに進められます。ここでは、実際に借用書や金銭消費貸借契約書を公正証書に格上げする場合の流れを、実務に即して整理します。
まずは、契約条件の整理から始めます。貸主・借主の基本情報に加え、元本額・返済期日・返済方法(振込か現金か)・利率(利息制限法の範囲内)・遅延損害金の利率・期限の利益喪失条件・連帯保証人の有無・担保設定(不動産・動産・売掛金など)を明確にまとめておきましょう。これらの条件が曖昧だと、公正証書の効力が弱まるだけでなく、公証役場とのやり取りが長引いてしまいます。
次に、公証役場への事前相談・予約を行います。電話やメールで問い合わせ可能ですが、近年は契約書の草案をメール添付で送ると、公証人が事前に内容をチェックして修正点を指摘してくれるため、非常にスムーズです。特に「強制執行認諾文言」を入れる場合は、適切な表現になっているか事前確認をしておくことが重要です。
当日は、貸主・借主(および連帯保証人)が公証役場に出向き、面前で契約内容を最終確認します。問題がなければ署名・押印を行い、正本と謄本を受け取ります。正本は強制執行の際に必要となる書類なので、必ず大切に保管しましょう。
万が一、返済の滞納が発生した場合には、公正証書に「強制執行認諾文言」が入っていれば、裁判を経ずに差押え等の強制執行に移行できます。具体的には、執行文付与の手続きを経て、裁判所に強制執行申立てを行う流れです。これにより、給料や預金、不動産などの差押えが可能となり、回収力は通常の借用書とは比べものにならないほど強力です。
このように、公正証書は条件整理 → 公証役場での予約・相談 → 面前で署名押印 → 滞納時の強制執行という流れで進みます。事前準備を怠らず進めれば、個人間融資の安全性を飛躍的に高めることができます。
公正証書は、借用書や金銭消費貸借契約書よりも強力な法的効力を持つ契約文書ですが、作成の過程でミスがあるとせっかくの効力が弱まったり、強制執行できなくなるリスクがあります。ここでは、公正証書を活用する際に絶対に避けたいNGポイントを整理します。
まず注意すべきは、利息・遅延損害金の設定です。利息制限法の上限を超える金利や、違法な遅延損害金を盛り込んだ契約は無効とされる可能性があります。借主が返済を怠った場合でも、違法条項が含まれていると裁判所が認めず、執行力が失われかねません。必ず法定上限内で設定しましょう。
次に、住所・氏名・口座名義などの記載ミスも致命的です。公正証書はそのまま強制執行に利用する「債務名義」となるため、たとえば借主の住所が誤っていると、裁判所での手続きが止まり、差押えができない事態に陥ります。契約当事者の氏名・住所・生年月日・銀行口座情報は必ず正確に記載し、身分証と突き合わせて確認しましょう。
また、相手が「公正証書まで作るのは大げさだ」と渋るケースもあります。その場合は、「お互いの安心のため」「トラブル予防のため」と説明することが効果的です。貸主だけでなく、借主にとっても「条件が明文化されることで不当な請求を避けられる」というメリットがあると伝えると理解を得やすくなります。
さらに、高額の貸付や担保付き融資、複雑な契約条件を盛り込むケースでは、行政書士や弁護士などの専門家によるリーガルチェックを受けておくと安心です。専門家に確認してもらうことで、契約無効や執行不能といったリスクを大幅に下げられます。
結論として、公正証書(強制執行認諾付き)は裁判不要で執行可能な「最強の回収ツール」です。借用書や金銭消費貸借契約書と併用することで、証拠力・回収力・スピードを最大化できる二段構えの安心体制が完成します。個人間融資のリスクを最小化したいのであれば、公正証書の活用は欠かせません。
借用書に収入印紙は必要?
借用書や金銭消費貸借契約書を作成する際に、多くの人が疑問に思うのが「収入印紙は必要なのか?」という点です。結論から言えば、金銭の貸し借りを証明する文書には印紙税法に基づき収入印紙の貼付が必要 です。
ただし、収入印紙を貼らなかったからといって、その借用書や契約書そのものが無効になるわけではありません。契約自体の効力は有効に成立します。問題となるのは、印紙税の納税義務を果たしていない状態になる という点です。
印紙税を貼らないとどうなる?
もし収入印紙を貼らずに借用書を作成・使用してしまうと、印紙税の納付漏れ と見なされます。税務署に発覚した場合、通常の印紙税に加えて 過怠税(ペナルティ) が課されることになります。
過怠税の計算方法は、
- 本来納めるべき印紙税額
- +その2倍に相当する金額
です。つまり、必要な印紙税の 3倍 を支払うリスクがあるのです。これは少額の貸し借りであっても決して軽視できません。
借用書に必要な収入印紙の金額
借用書や金銭消費貸借契約書に貼る収入印紙の金額は、借入金額によって異なります。印紙税法別表第一「第7号文書」に基づく主な区分は以下のとおりです。
- 1万円未満:非課税
- 1万円以上100万円以下:200円
- 100万円超〜200万円以下:400円
- 200万円超〜300万円以下:1,000円
- 300万円超〜500万円以下:2,000円
- 500万円超〜1,000万円以下:10,000円
- 1,000万円超〜5,000万円以下:20,000円
(※最新の税制改正で変更される可能性があるため、必ず国税庁の公式サイトで確認してください。)
なぜ収入印紙が必要なのか?
収入印紙は「契約書の内容に課税する」ための制度です。特に金銭消費貸借契約書は、金銭の貸借に関する重要な課税文書 にあたるため、印紙税が課せられる対象になります。
これは、単なる形式的な義務ではなく、税務上のコンプライアンスを守るための必須手続き ともいえます。印紙税を怠ると、後々の税務調査で余計なトラブルを招きかねません。
- 借用書・金銭消費貸借契約書には収入印紙が必要
- 貼らなくても契約の効力は有効だが、印紙税法違反となる
- 発覚すれば「印紙税+その2倍=3倍の過怠税」を課される
- 借入額に応じた正しい金額の収入印紙を貼付することが大切
借用書を作成するときは、法的効力だけでなく税務上のリスクも考慮し、適切な収入印紙を貼付することが安心への第一歩 です。
さいごに
以上、個人間のお金の貸し借りにおける借用書・金銭消費貸借契約書の作成方法と注意点 をご紹介しました。
お金の貸し借りは、たとえ親子・兄弟・親友といった身近な関係であっても、人間関係を壊す大きなリスク を伴います。民法上は口約束でも契約は成立しますが、実際には「言った・言わない」のトラブルが頻発し、最悪の場合には裁判や縁切りにまで発展するケースも少なくありません。
そのような不安を回避するためには、必ず書面で契約内容を残すことが最重要 です。借用書や金銭消費貸借契約書を作成しておけば、返済期日や金利、返済方法、遅延損害金などが明確化され、双方が安心して契約を履行できます。また、万一返済が滞った場合にも、裁判の証拠として効力を発揮 するため、法的にも有利に働きます。
なお、契約書の作成を相手に提案した際に「信用していないのか」と感情的になる人もいますが、そのような態度こそ 返済能力や誠実さに欠けるサイン です。信頼できる相手であれば、書面を残すことに納得してくれるはずです。
結論として、どんなに親しい間柄でもお金を貸す際には必ず借用書や金銭消費貸借契約書を作成すること をおすすめします。冷静な準備がトラブルを防ぎ、あなたの大切な人間関係と資産を守る最良の方法となるでしょう。